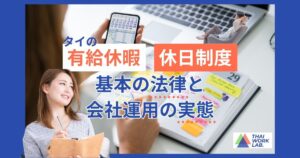タイの医療保険制度とは?社会保険・民間保険の違いと選び方を徹底解説

タイで働く場合、病院にかかるときに使える医療保険には「社会保険」と「民間保険」の2種類があります。
どちらにも特徴と制限があり、加入方法・補償範囲・使いやすさが異なるため、自分に合った組み合わせを理解することが大切です。
本記事では、タイの医療保険制度の概要、社会保険との違い、民間保険の選び方について解説していきます。
タイの医療保険制度の全体像
タイでは、労働者が安心して働けるように複数の医療保険制度が整っており、主に以下の2種類に分類されます。
- 政府が運営する社会保険(Social Security)
- 企業または個人が加入する民間医療保険
社会保険は給与から自動的に天引きされ、指定病院での治療が基本的に無料。
一方で、民間保険は補償範囲が広く自由に病院を選べる点が魅力です。
タイにある外資系企業では福利厚生として民間保険が付与される場合もあります。
この章ではタイの医療保険制度の全体像として、上記の保険について解説します。
政府による社会保険(Social Security)
社会保険(Social Security)は、雇用者と被雇用者がそれぞれ給与の5%を拠出し、医療・失業・年金などをカバーする制度です。
登録された指定病院を利用すれば、診察・治療・薬代などが無料または低額で受けられます。
外国人労働者も加入対象であり、タイで働く人にとって最も基本的な医療保障といえるでしょう。
拠出額の上限は750バーツとなっているため、月給が15,000バーツ以上の人は全て750バーツの社会保険料となります。
企業が提供する民間保険
タイにある外資系企業や大手タイ企業の多くは、従業員向けに団体医療保険を導入しています。
これは会社が保険料の一部または全額を負担し、より良い病院を自由に選べる保険へ加入させてくれる制度です。
社会保険より補償上限が高く、外国語対応の私立病院でも使えるケースが多いのが特徴。
タイで働く日本人の多くは、会社が負担してくれるこの保険を活用して、日本語サービスのある私立病院を受診しています。
個人加入の民間医療保険
自営業者や社会保険が適用されない人は、個人で民間保険に加入できます。
また、会社負担の保険では補償が足りないと感じる方が、個人で民間保険に加入するケースもあり。
タイ国内の保険会社や海外の保険会社の商品を選択可能で、タイにある代表的な保険会社には下記の通りです。
(保険会社名クリックで各社のWebサイトへ移動します。)
保険料は年齢やプランによって異なり、入院・手術・外来・歯科など、希望に応じて柔軟にカスタマイズできます。
会社負担の保険プランに自費を追加し、補償額の増額やプランの追加などの対応ができる場合もあり。会社で民間保険に加入している上で個人保険に加入したい場合は、まず人事に相談してみるのがベターです。
駐在員向けの海外旅行保険との違い
駐在員が加入する海外旅行保険にも長期プランがありますが、基本的に1年ごとの更新となります。
保険料はタイの民間医療保険と比較すると割高な場合が多く、書類郵送などの作業が発生した際に国際郵便となるデメリットもあります。
一方で、飛行機遅延やロストバゲージへの補償など、一時帰国時にあると安心できる補償が付いているのが魅力です。
しかし、毎年日本側と連絡を取って更新等の手続きが必要となる面倒さを考えると、現地で民間医療保険へ加入する方がおすすめです。
社会保険の医療補償とは?
社会保険は、政府が管理するタイの公的医療制度です。
会社員として雇用契約を結んでいれば自動的に加入対象となり、医療費を大幅に軽減できます。
ただし日本の制度とは少し異なり「指定病院制」や「補償上限」などがあるため、利用時のルールを理解しておくことが大切です。
タイの社会保険制度については以下の記事で詳しくご紹介しているので、ここでは簡単にご紹介しようと思います。
社会保険でカバーできる範囲
社会保険では、通院・入院・手術・薬の処方など、基本的な医療費が無料になります。
さらに、妊娠・出産、歯科治療(年上限あり)にも対応しており、高額医療費の心配が少ないです。
日常的な病気やけがには十分な補償内容といえます。
日本とは異なる「指定病院制」とは
社会保険は「登録された病院でのみ利用可能」という指定病院制度を採用しています。
加入時に選択した病院で診察を受ける必要があり、他院を受診すると補償が受けられません。
病院の変更は年に1回可能です。
利用時には、身分証明書と社会保険カードを提示するだけで手続きが完了します。
補償上限と制限
基本的に無料とはいえ、社会保険には補償上限や制限があります。
例えば個室入院や高価な治療は自己負担が発生します。
また、英語対応の医師や私立病院は前述の指定病院制度で選べる対象外です。
(英語対応可能な病院も一部あり。)
高度な医療や快適さを求める場合には、民間保険の併用がおすすめです。
メリット・デメリット
社会保険の最大のメリットは、毎月の負担が少なく医療費がほぼ無料になることです。
一方で、社会保険で利用できる公立病院はいつも混雑しているため、受診するまでに何時間も待たなければなりません。また、受診できる病院が1か所に限られてしまうなどのデメリットもあります。
費用を抑えたい人には有用ですが、利便性やサービスを重視する人には物足りない面が多いです。
民間医療保険とは?
民間医療保険は、自由に病院を選びたい人や、社会保険の補償に不安がある人に向いています。
タイには多くの保険会社があり、プランも多様。
加入前に自分のライフスタイルと予算に合った内容を見極めることが重要です。
補償内容(部屋のランク、通院対応、手術費用など)
民間保険は、入院時の部屋のランク(個室・準個室など)を選べたり、私立病院の診察費・手術費用もカバーできます。
プランによっては、通院・予防接種・健康診断なども対象です。
日本語対応病院でも利用しやすく、多くの治療項目がキャッシュレスになるため、外国人にとって安心感があります。
補償金額の上限はプランによって異なりますが、雇用主が加入してくれる民間保険の場合、1日1回当たりの治療費の上限が1,000バーツ~3,000バーツ程度が一般的。
この金額は普通の風邪や軽いけがなどであればカバーできますが、インフルエンザやコロナウイルスのような感染症に伴う検査等が発生した場合は一部自己負担で支払いなどが発生するケースがあります。
また、プランによって保険適用外となる科もあるため、受診前に確認が必要です。
保険料と年齢・プランごとの目安
保険料は補償範囲によって異なります。
私が会社で加入して貰っているのは日系保険会社が出している年間50,000バーツ程のプランで、1日1回あたりの治療費上限が2,000バーツ、歯科治療などの補償も付帯しているものです。
1日1回あたりの治療費上限を下げて歯科治療の補償もなくせばもっと安くなるでしょう。
また、もっと手厚い補償を求める場合はもちろん年間の価格も上がります。
継続して同じ保険に加入する場合、前年に病院へ行った回数などによっても次年度の保険料の増減があるため、キャッシュレスだからと言ってむやみに病院へ行っていると、翌年の保険料が大幅に上がってしまうリスクあり。
どちらを選ぶべき?併用の考え方
タイで働く人にとって、社会保険と民間保険をどう組み合わせるかが重要です。
社会保険は最低限の安心を、民間保険は「選択の自由」と「快適な医療環境」を提供します。
自身の生活スタイルや勤務先の制度に合わせて、最適なバランスを考えましょう。
社会保険だけで足りる人
社会保険だけでも足りる人は概ね以下のような人です。
- タイ語での会話ができ、医師や受付でのコミュニケーションに困らない人
- 年間に数える程度しか病院へ行かない人
- 長い待ち時間が苦ではない人
- 日本の社会保険料支払いを継続している人(駐在員など日本にも籍が残っている人)※
※タイ移住後も日本の社会保険料の支払いを継続している場合、必要書類を日本で提出することで医療費の7割が戻ってきます。
(受診する科や治療項目が日本の保険適用項目である場合のみ)
民間保険を併用した方がよいケース
一方で民間保険を併用すべきケースは以下のような人です。
- タイ語で医師とコミュニケーションを取る事に不安がある人
- 高度医療サービスを提供している私立病院でないと心配だと思う人
- 持病がある人※
※持病がある場合、民間保険に加入しても治療費が保険適用外となる可能性があります。加入前に要確認。
もっとも良いのは、社会保険で基本部分を、民間保険で高額治療や入院時の快適さをカバーする「ダブル保険」です。
子ども・家族にも保険は必要?
家族帯同の場合、配偶者や子どもには社会保険が適用されません。
そのため、家族全員分の民間医療保険に加入することが大切です。
駐在員の帯同者としてタイへ来ている場合は、配偶者の雇用主によるサポートが受けられます。
現地採用の場合は家族分の保険加入サポートがあるかどうかを雇用主に確認する必要があります。なぜなら、多くの企業は家族分の保険までサポートしていない場合があるためです。
よっぽどの大手企業でない限り、家族分の民間保険加入費まで企業が負担してくれる事は無いので、個人で民間医療保険に加入する事となるでしょう。
まとめ
タイの医療保険制度は、社会保険で基本をカバーし、民間保険で快適さを補うのが理想的です。
費用を抑えたい人は社会保険中心で、サービスや利便性、質を重視する人は民間保険の併用を検討しましょう。
勤務形態・家族構成・生活環境に合わせて、自分に合った保険選びを行うことが、タイで安心して暮らす第一歩です。
タイワークラボ編集部

在タイ日系人材会社で働く日本人が、「タイで働く」「タイで暮らす」日本人のためのリアルな情報を、現地からお届けしています。
人材業界での実務経験や在住者の視点を活かし、キャリア・制度・くらしなど幅広いカテゴリをカバー。今タイで働いている人だけでなく、将来的にタイでの就職・移住などを考えている方にとってもヒントになるような記事を目指して、日々コンテンツを発信中です。