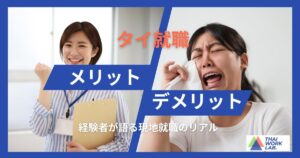タイの社会保険制度とは?概要・保険料・加入条件など徹底解説

タイで働く日本人にも「社会保険」の加入義務があります。
日本の制度とは異なる点も多く、「何がカバーされてるの?」「どれぐらい払うの?」と戸惑うことも。
この記事では、タイの社会保険制度の基本情報から保険料、保障範囲、注意点までを詳しく解説します。
この記事の目次
タイの社会保険制度とは?
まず、「タイの社会保険制度とは何ぞや?」という点からです。
タイの社会保険制度の概要
社会保険制度(Social Security System)は、労働者の生活を守るために設けられた公的保険制度。タイで働く外国人も、条件を満たす場合は加入が義務付けられている制度です。
健康保険、年金、失業給付、出産手当などをカバーしており、日本の社会保険に近い仕組みを持っています。
社会保険に加入することで、病気やけが、失業といった予期せぬ事態にも備えることができるでしょう。
加入対象者の定義
社会保険への加入は、民間企業で雇用されている従業員(タイ人・外国人を問わず)が対象です。
原則として、1人でも従業員を雇う企業は社会保険事務所に登録し、給与から保険料を控除して納付する必要があります。
自営業者や企業の代表者は強制加入の対象外ですが、自主的に任意加入できる制度も用意されています。
いつから加入する?
従業員が企業に雇用された時点で、就業開始から30日以内に加入手続きを行う必要があります。
企業側が社会保険事務所に申請を行い、従業員は自動的に被保険者となるため、従業員側が何か特別な手続きを行う必要はありません。
加入後には社会保険番号が発行され、各種給付を受けられるようになります。
保険料と保障内容
次は気になる保険料と保障内容についてです。
日本で給与から天引きされる健康保険料と比較すると、かなりお財布に優しい金額なのがタイの社会保険。
保障内容についてもしっかり把握しておきましょう。
保険料率
社会保険料は、給与の一定割合(※1)を基準に計算されます。
一般的な保険料率は以下の通りです(2026年1月時点の標準例)
- 従業員負担:給与の5%(上限875バーツ)
- 会社負担:給与の5%(上限875バーツ)
- 政府負担:2.75%
つまり、企業と従業員の双方が負担し、国も一部を補助する仕組みになっています。
(※1)給与とは毎月の基本給と固定で支給される各種手当の総額から算出されます。毎月の残業・勤怠・業績により変動する手当は算出の対象外です。
実際に引かれる金額の目安
例えば、月給20,000バーツの従業員の場合、5%にあたるのは1,000バーツです。しかし上限が750バーツなので、給与から控除されるのは875バーツ(※2)となります。企業側も同額を負担します。
収入により社会保険料が変動するのは給与が17,000バーツ未満の方に限られるため、日本人の場合は一律875バーツと覚えておいても良いでしょう。
(※2)2026年1月1日より適用。負担率は5%のままで、2025年12月までは上限750バーツです。
カバーされる保障内容
社会保険に加入すると、以下のような保障を受けることができます。
- 医療費の補助:指定病院での治療無料
- 出産手当:日給の60日分を負担
- 障害給付
- 失業給付:一定条件あり
- 老齢年金:一定条件あり
- 遺族給付
医療費や年金だけでなく、失業や出産といったライフイベントも幅広くサポートしているのが特徴です。
社会保険を使うには?実際の使い方
タイ人だけでなく外国人も加入対象があり、保障を受けることが出来るタイの社会保険ですが、実際に使いたい時はどうやって使ったらよいのでしょうか。
もっとも利用する可能性が高い「医療費の補助」について解説していきます。
指定病院制度について
社会保険では「加入者本人が毎年更新されるリストから希望の指定病院(one selected hospital)を1か所だけ選ぶ」仕組みです。
この指定病院を通じて医療サービスを受ければ、病気や怪我の治療費が無料になります。
指定病院以外を利用すると、原則として自己負担になりますので注意が必要。
日本の制度の様に加入していればどこの病院でも保障が受けられるわけではないということを覚えておきましょう。
指定病院について
社会保険の指定病院はタイにある全ての病院から選べるわけではなく、リストに載っている公立病院とごく一部の私立病院のみから選ばなければなりません。
日本人が通っているような通訳常駐の私立病院はこの指定病院リストには載っていないので、選ぶ際は自宅からのアクセスの良さを基準に選ぶしかないかと思います。
なお、指定病院は年に1回変更手続きができるので、仮にタイ国内で引っ越した場合でも病院の変更ができ安心です。
加入時の登録とカードの使い方
加入が完了すると、社会保険番号が付与され、社会保険カード(または電子証明)が発行されます。
病院で診察を受ける際は、このカードと身分証明書を提示することで、医療費が免除または大幅に軽減されます。
外国人が帰国時に受け取れる社会保険料の一時金
タイの社会保険制度では60歳以上に年金が受給される仕組みがあります。しかし外国人の場合は年金が受給される年齢までタイにいない可能性があるため、帰国時に老齢年金の一括払いの手続きを行うことが出来ます。
対象者
一時金(老齢年金の一括払い)を受け取ることが出来る対象者は下記の通り。
- タイの社会保険に加入していた外国人労働者
- 60歳未満で帰国、かつ納付期間が180か月(15年)未満 の場合
ちなみに納付期間が15年以上になると一時金としての払い戻しができず、年金受給の選択肢しか無くなります。
受給内容
納付した期間に応じて、自己負担分と会社負担分がまとめて返金されます。
- 自己負担分(給与から天引きされた額)
- 会社負担分(雇用主が納付した額)
※政府負担分は返還されません。
仮にタイで5年間働いた人の場合だと、下記のような計算になります。
自己負担分:45,000バーツ(750×12か月×5年) + 会社負担分:45,000バーツ(750×12か月×5年)=合計:90,000バーツ(※3)
(※3)2026年1月より社会保険料の上限が875バーツになるため、社会保険料を納付していた時期によっては上記計算式が当てはまらない場合があります。
手続きの流れ
手続きの流れは下記の通りです。
- 帰国前または帰国後に社会保険事務所(SSO)で申請
- 必要書類を提出(パスポート、ワークパーミット、銀行口座情報など)
- 承認後、指定口座に送金(海外送金可能)
帰国後の手続きも可能ですが、在タイ大使館の認証や追加書類が必要になるケースがありとても大変です。可能であれば帰国前に忘れずに申請を出しておきましょう。
まとめ
タイの社会保険制度は、従業員・企業・政府が共同で負担し、医療・年金・失業など幅広い保障を提供する仕組みです。
給与から天引きされる金額は上限があり、大きな負担にはなりにくい一方で、医療費や失業給付などの恩恵を受けられる点が大きなメリット。
タイで働く以上、外国人も含めて加入は必須となるため、制度の内容や利用方法を正しく理解しておくことが安心につながります。
タイワークラボ編集部

在タイ日系人材会社で働く日本人が、「タイで働く」「タイで暮らす」日本人のためのリアルな情報を、現地からお届けしています。
人材業界での実務経験や在住者の視点を活かし、キャリア・制度・くらしなど幅広いカテゴリをカバー。今タイで働いている人だけでなく、将来的にタイでの就職・移住などを考えている方にとってもヒントになるような記事を目指して、日々コンテンツを発信中です。