タイの有給休暇・休日制度の基本と実務対応|法律と会社運用の実態

タイで働くときに気になる「有給は取れるの?」「祝日はどれくらい?」という疑問。
実はタイにも日本と同様、法律で決められた有給・休日制度があります。
本記事では、タイ労働法に基づく休暇・休日の基本ルールと、実際の企業での運用実例、注意点までをわかりやすく解説します。
タイの休日制度の基本
まずはタイの休日制度についてです。
以下では週休と祝日について、タイの労働者保護法の内容に基づき説明します。
週休
タイの労働者保護法によると、法定労働時間と週休日は以下の様に定められています。
- 法定労働時間:1日8時間以内・1週間48時間以内
- 週休日:6日を超えて連続して勤務する事は出来ない(週休1日)
法令上は週6日勤務(週休1日)が可能ですが、多くの会社では月の休日数を6日~8日の間に設定していることが多いです。
つまり、土日が完全に休みになっている会社や、土曜が隔週休みまたは月1回程度出勤となっている会社が多いということ。
バンコクにあるオフィス勤務の場合は土日が完全に休み、郊外の製造業などでは土曜に出勤日を設けているケースが多い印象があります。
完全週休1日になっている会社は、日系企業よりもローカル企業に多い傾向もあります。
祝日
タイの法定祝日は年間13日以上ですが、年間の祝日数は13日以上あります。
そのため、タイのカレンダー通りに祝日を休みとする会社と、法定祝日13日間を休みとし、あとは出勤日に設定する会社がある印象です。
また、タイでは突然その年だけ祝日が増えることが毎年のように発生します。このようなイレギュラーな祝日に関しても休みとするか否かは会社によって判断が分かれます。
製造業に関して言うと、生産効率や機械の稼働効率などを加味して年間のカレンダーを作成するため、割とフレキシブルに祝日が動く印象。
たとえば週半ばの祝日を出勤日とする代わりに週末を振替休日としたり、飛び石連休になっている箇所に特別休暇を加える代わりに別の週の土曜を出勤日にしたりなどです。
上記のような対応はとりますが、どの企業もミニマム13日の祝日は確保した上で運用しています。
有給休暇(Annual Leave)のルール
タイ労働者保護法では、法定休日と祝日の他に様々な休暇制度が設けられています。
代表的なもののひとつが有給休暇(Annual Leave)です。
付与の条件(1年以上勤務)
タイの法律では、正社員が1年以上勤務すると年次有給休暇を付与する必要があると定められています。
法律通り勤続1年以上で有休を付与する会社が一般的ですが、中には勤続半年以降付与されるケースや、試用期間(119日)が終わったタイミングで付与されるケースもあり。
1年以上経過での付与は義務ですが、それよりも前に付与するか否かは会社の判断に委ねられています。
付与日数と時期
法令で定められる有給日数は年間最低6日です。
勤続年数が増えると日数が増える会社もありますが、日本のように消化しきれない程たくさんの有給休暇が付与されるのは稀なケース。
付与日は勤務開始日や年度単位で計算され、会社によって異なる運用があります。
繰越・失効のルール
タイの法律では消化しきれなかった有給休暇は買取りしなければならないとなっています。
しかし、会社で繰り越しのルールを設けている場合、買取りの必要はありません。
繰り越しのルールがない上に買取りもできないというのは法令違反となるため、もし自社の運用がそのようになっている場合は弁護士等に確認する必要があります。
有給の取得や買取りのルールは就業規則に必ず記載されているので、まずは社内規定上の運用ルールを確認しましょう。
特別休暇とその扱い
有給休暇の他に法令では以下の休暇を付与することが定められています。
- 病気休暇/傷病休暇(Sick Leave)
- 用事休暇(Business Leave)
- 出産休暇(Maternity Leave)
- 不妊手術を受けるための休暇
- 兵役休暇
- 研修または知識・能力向上のための休暇
休暇期間中が有給か無給かは休暇の種類により異なりますが、多くの人に当てはまる代表的な3つの休暇を見ていきましょう。
病気休暇(Sick Leave)
病気休暇/傷病休暇(Sick Leave)は、怪我や病気をした場合に取得できる休暇です。
年間30日以上付与することが義務付けられています。
これは勤続年数に関わらず一律で付与され、入社してすぐに取得する事が可能です。
ただし、連続して3労働日以上の傷病休暇を取得する場合は診断書を提出する義務があります。
裏を返すと1、2日の傷病休暇の場合は診断書不要なので、頭痛や腹痛など軽い症状でも簡単に会社を休む事ができてしまいます。
(このような背景から、シックリーブを「サバイサバイ休暇」などと揶揄する人も。。。)
こちらは休暇は有給ですが、消化しきれなかった場合の買取りや繰り越しはありません。
用事休暇(Business Leave)※法的に認められている。
用事休暇(Business Leave)は、私用や公的な用事での休暇です。付与日数は年間3日以上で、Sick Leaveと同様に入社後すぐに取得可能。
この休暇は、どうしても平日にしなければならないことが発生した場合に取得できます。
たとえば役所での手続き業務や、免許の更新など。
法律上の休暇取得の基準が曖昧なため、細かな運用方法は会社により異なります。
出産休暇
出産休暇は女性社員に対して法律で最低98日が保障されています。
会社が有給扱いにしなければいけないのはこの98日のうちの45日分。残りの日数分は本人が社会保険庁へ申請することで給付金を受け取ることが出来るようになっています。
タイは育児休暇が無いため、日本と比較すると妊娠出産に関する休暇日数はかなり短いです。
※2025年12月7日より、出産休暇の日数が120日へと変更。これにより企業負担は60日分、社会保険からの給付金も60日分となります。
また、男性についても、配偶者が出産した場合に最大15日間の休暇を取得することが法律で認められるようになります。
結婚・忌引など会社が任意で定めるケースも
その他、上で挙げた休暇は取得する権利がありますが、基本的に無給となります。
また、会社によっては結婚休暇や慶弔休暇などを有給として定めているケースもあり。
福利厚生の充実している会社ではお誕生日休暇などユニークな休暇を設けている例もあります。
各休暇の種類や取得基準などは各社の就業規則に明記されています。
人事担当・管理職向け:実務での注意点
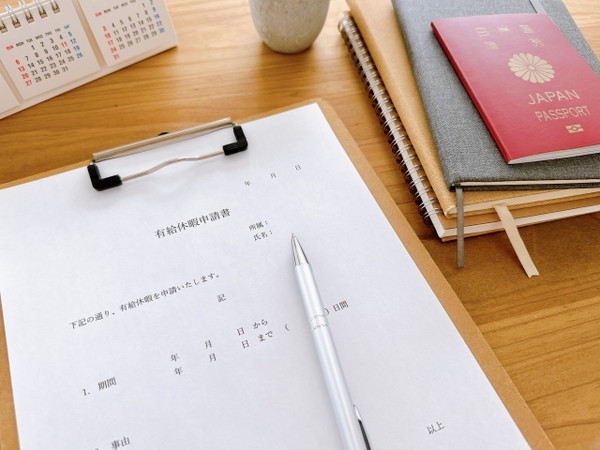
休暇の種類は法令で定められているもの以外にも様々。企業の管理者や人事担当者は各休暇の運用についてきちんと把握しておく必要があります。
以下では、休暇管理における実務上の注意点についていくつか例を挙げてまとめています。
休暇申請書と記録の管理
休暇申請書や承認記録を整備することは、人事管理の基本です。
ここを怠ることでトラブルに繋がるケースもありますので、紙でも電子でも、取得日数や残日数がすぐ確認できる仕組みを整備しておきましょう。
全てを日本人管理者マターにする必要はありませんが、タイ人スタッフ任せにしているとブラックボックス化してしまうケースもあり。
自社の休暇管理が正しい方法で行われているかどうかだけは、自身の目で確かめておいた方が安心です。
有給残日数の可視化
社員が残日数を確認できる仕組みは、取得計画や調整に役立ちます。
特に外国人社員は自国制度と異なるため、正確な可視化が信頼関係維持にもつながります。
申請時のトラブル回避策
よくあるトラブルとして、休暇申請の拒否によるスタッフからの不満などがあります。
これは人事がスタッフへ休暇申請のルールを周知できていないことが原因。
スタッフの入社時に就業規則に沿って休暇申請ルールを伝えるのは必須事項です。
加えて、いつでもルールが確認できる仕組みを社内で整備するのもトラブル回避に繋がります。
各休暇を取得できる条件(用事休暇を取得できるケース例や、産休申請に必要な書類など)や、申請期日(休暇取得日の〇日前までに申請)などを明記しておくことが大切です。
書面や社内掲示などでわかりやすく記載しておくことで、スタッフごとの理解や認識のズレがなくなるため、大きなトラブルやスタッフの不満のタネとなる事を防ぐことが出来ます。
休暇取得に関するよくある質問
最後に、有給を始めとする各種休暇の取得に関するよくある質問例をまとめてみました。
試用期間中に有給はある?
法令で定められているのは「勤続1年以上で6日以上付与」ですので、試用期間中は有給休暇が付与されません。
ただし会社規定で付与する場合もあるため、入社時に確認することをおすすめします。
有給は買い取りしてもらえる?
法律上は毎年買取りする必要があるとなっていますが、有給の繰り越しができる会社の場合は買取り不可の場合もあります。
買取り不可の場合でも、退職時など一部例外はあります。
基本的に退職時に有給を消化してもらうように会社は促しますが、業務の引継ぎ等の都合などで退職前に有給を消化できない場合は、買取りをお願いすることが出来るケースもあり。
会社によって有給運用の規定が異なるため、人事に確認するのがベターです。
転職時に有給をまとめて取ってもOK?
退職前に有給をまとめて消化できるかは会社の運用次第です。
業務調整が可能か確認し、承認を得ることが必要です。
日本人にだけ有給少ないなんてある?
法律上は差別禁止です。
日本人だけ有給が少ない場合は、就業規則や労働契約に違反する可能性があるため注意が必要です。
まとめ
タイの休暇制度は法律で最低限の基準が決まっていますが、定義は曖昧な部分が多いです。
実際の運用は会社ごとに大きな差があります。
人事担当者や管理職は、規定の理解と正しい運用、記録管理を徹底することで、トラブルを防ぎつつ円滑な休暇取得を支援できます。
社員への周知方法も重要なポイントですので、忘れずに覚えておきましょう。
タイワークラボ編集部

在タイ日系人材会社で働く日本人が、「タイで働く」「タイで暮らす」日本人のためのリアルな情報を、現地からお届けしています。
人材業界での実務経験や在住者の視点を活かし、キャリア・制度・くらしなど幅広いカテゴリをカバー。今タイで働いている人だけでなく、将来的にタイでの就職・移住などを考えている方にとってもヒントになるような記事を目指して、日々コンテンツを発信中です。


